
(M.Seki)
第81代日本ダービー馬ワンアンドオンリー。頂点に上り詰めるまでにどのような軌跡を辿ってきたのか。育成時代を過ごした大山ヒルズのスタッフと、橋口弘次郎厩舎で同馬を担当する甲斐純也調教助手に話を伺い、その内側に迫った。
(石田敏徳=文 text by Toshinori Ishida)
驚異的なスピードで輝いた能力の珠
13年のキズナに続いて14年もまた、「鳥取育ちのダービー馬」が誕生した。ノースヒルズの生産馬によるダービー制覇が2年連続なら、その育成拠点として知られる大山ヒルズ(鳥取県)の育成馬によるダービー制覇も2年連続。「1世代あたりの頭数は約70頭」(齋藤慎ゼネラルマネージャー、以下GM)という規模で運営されている育成牧場にとって、ダービーの連覇が"奇跡的"といえる快挙であることは改めて記すまでもない。
(I.Terashima)

生産拠点のノースヒルズ(北海道新冠町)で初期の馴致までを済ませたワンアンドオンリーが、大山ヒルズにやってきたのは1歳の夏の終わりだった。齋藤GMによれば翌年の冬にかけて五月雨式にやってくる同期生のなかでは「トップバッターに近い組」だったそうで、怪我や病気などのアクシデントとは無縁のまま、成長してきたことが窺える。
山陰の名峰・大山の麓に広がる牧場に移動してきた馬達は、初歩的な乗り馴らしを済ませ、十分にハンドリングを行った後、坂路コースでの調教へと向かう。ワンアンドオンリーも1歳の9月半ばにはもうすでに、坂路コースを駆けあがっていた。大山ヒルズでは、1歳の若駒達でも2~3頭併せで調教するので、闘争心があおられ、この時期としてはかなり速い時計がマークされることもある。
これに慣れてくると、砂厚が深めの周回コース(ダート)での集団調教が行われ、馬群の中でも折り合うこと、乗り手の指示に従うことを覚えるとともに、一方ではさらなる負けん気も養われるのだ。「だからウチの馬には勝負根性が旺盛なタイプが多いでしょう? 馬体を併せる形になったら、少しでも前に出ようとする気持ちが強いんです」
懸命の抵抗を続けたイスラボニータを競り落とし、勝利をつかんだダービー。あの粘り強い末脚の原点がここにある。
もっとも、"ノースヒルズの最高傑作"とまで評された通りのオーラを放っていた前年のキズナに対し、牧場時代のワンアンドオンリーは決して目を引く存在ではなかったという。
「飛節の折りが深くてバネはありそうな感じでしたが、馬体の見た目は線が細くて、華奢な印象が先に立っていました。それにキャンターで走らせるとまだ身体を上手に使えず、推進力が上へ逃げる感じになってしまっていたんです。ここにいた時点では"これは"という手応えまでは持てませんでした」と齋藤GMが振り返れば、獣医師として毎日、馬を診ていた長高尚マネージャーも「何かの治療をした記録も記憶もなく、その意味ではすこぶる順調だったわけですが、特別に印象に残る馬ではありませんでした」と率直に明かす。
そんな2人が口を揃えて指摘した思い出が「とにかくよく立ち上がっていた」こと。大山ヒルズではチームとしての一体感を高めるため、馬の乗り手をできるだけ固定しない方針を貫いており、スタッフはほぼ全員、未来のダービー馬に騎乗した経験を持つ。当時の情景が脳裏に浮かんだのだろう。「みんな、とにかく落とされないようにと必死であの馬に乗っていました」と齋藤GMが笑った。
ただしスタッフを手こずらせたやんちゃな習性には、華奢で頼りなげに映る見た目とは異なる一面が示されてもいた。
「1歳の時期に立ち上がると、後ろ脚だけでは身体を支えきれずにひっくり返ったりもするのですが、あの馬はそんなことはありませんでした。見た目以上に(筋力が)強く、馬も自分で加減して立ち上がっていたのでしょう」(齋藤GM)
「立ち上がるときでも何かに驚き、パニック状態に陥っているのではなく、乗り手を試しているだけ。馬は理性を保っていて、肝は据わっているほうだったのかもしれません」(長マネージャー)
(M.Yamada)

2歳の3月上旬、大山ヒルズで撮影されたデビュー前のワンアンドオンリー。 まだ筋肉が付き切っておらず、どこか頼りない印象もあったが、先々は走っ てきそうな雰囲気があったという
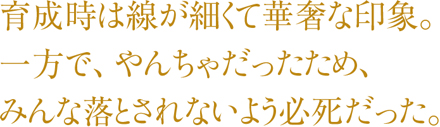
完成度は決して高くないけれど、伸びしろは大きい。そのことも含め、先々は走ってきそうなイメージを描くことはできた。とはいえ、「明らかに奥手のタイプ」というのが2人の共通認識で、だから2歳の5月、大山へやってきた橋口弘次郎調教師から早めの入厩を打診されたときには、「時期尚早かもしれません」と、牧場としての見解を伝えた。「でも橋口調教師は『こういう馬は早くに競馬を覚えさせたほうがいいし、試しに一度、やってみる』とおっしゃって。それであの時期に入厩させることになったんです」(齋藤GM)
こうして早期のデビューを目指すことになったワンアンドオンリーが栗東トレセンに入厩したのは昨年の6月1日。トレーナーの積年の悲願を連想せずにはいられない、美しい名前をつけられた馬は、1年後にダービーを勝つことになるまさにその日に、新たな一歩を踏み出したのだ。
8月の小倉で迎えた初陣ではレース前から激しくイレこみ、早々に手応えを失って12着に大敗したワンアンドオンリーだが、一度、実戦を経験したことで競馬を理解したのだろう。2戦目の未勝利戦では13番人気(単勝260.1倍)という低評価を覆して2着に好走。3戦目で勝ち上がり、昇級初戦の萩Sでもハナ差の2着に食い込むと、東京スポーツ杯2歳Sの6着を挟んでラジオNIKKEI杯2歳Sを鮮やかに差しきり、ダービー候補の1頭に名乗りをあげる。牧場時代にはとても想像できなかった早さと速さで、輝きを増していった能力の珠。その過程において大きな役割を果たしたのは、持ち乗りで担当する甲斐純也調教助手である。
父の正文さん(故人)はかつて橋口厩舎で、ダイタクリーヴァをはじめとする数々の活躍馬を担当した腕利き厩務員。橋口調教師がダービーに送り込んだ初めての管理馬ツルマルミマタオー(90年4着)も正文さんの担当馬だった。そんな父の背中を見て育ち、「保育園の頃にはもう、競馬の世界へ進むことを決めていた」という甲斐さんは、なかなかユニークな価値観を持つ。「おとなしい性格をしていて、レースでも走ってくれる馬より、たとえ走らなくてもうるさい性格をしている馬のほうが僕は好きですね」
トレセンに入厩してからも立ち上がったり、尻っぱねをしたりなどの悪さを盛んに繰り返していたワンアンドオンリーだが、甲斐さんは"元気の証拠"と受け止め、無闇に叱ったりはしなかった。反面、自分の言うことを聞いてくれたときには褒めてあげる。そのように接することによって、彼は馬との絆を徐々に深めてきた。やんちゃな馬とコミュニケーションを築いていくことに、この仕事の楽しさを感じると笑う彼は、まさにうってつけの担当者だった。「やんちゃはやんちゃでも、人間に危害を加える意志はなく、馬にしてみればただふざけているだけ。褒められたということはちゃんと理解しているし、学習能力も高い。マイペースというのか、レースや調教の後はつけたカイバを完食するとすぐに寝てしまう。これでけっこう、分かりやすい性格なんです(笑)」
(K.Ishiyama)

チーム・ノースヒルズにとってダービー2連覇。多くの関係者の笑顔が溢れる口取り撮影となった
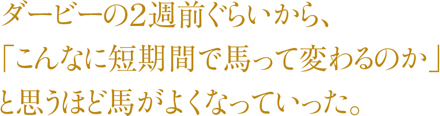
(I.Terashima)

走ることが大好きで、調教やレースに対して拒否反応を示したことは一度もない。特に他の馬を追いかけたり、併せる形になると、負けん気を振り絞って一所懸命に走ってくれる。ハードな調教を課してもすぐに息が入るように心肺能力も高い。大きな素質の片鱗は2歳時から随所に感じていた甲斐さんが、馬の変化と成長を実感したのは3歳の2月、弥生賞の1カ月ほど前だったという。「2歳時に比べると必要な筋肉がつき、身体をうまく使えるようになりました。それにつれて重心の低いフォームに変わってきたし、走るときの身体の"ブレ"もなくなってきました」
(N.Inaba)

担当の甲斐純也調教助手は、やんちゃな馬の方がやりがいがある、と語る。ワンアンドオンリーとの相性も良かったのだろう